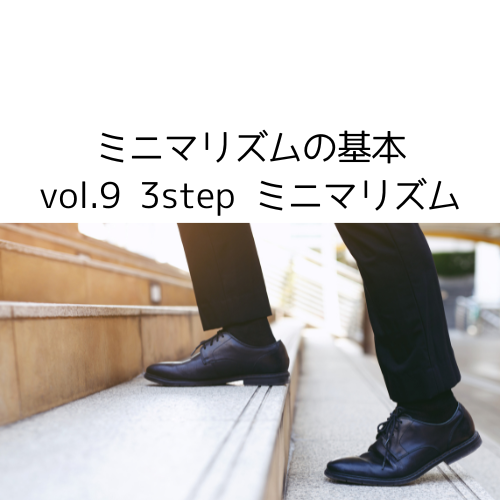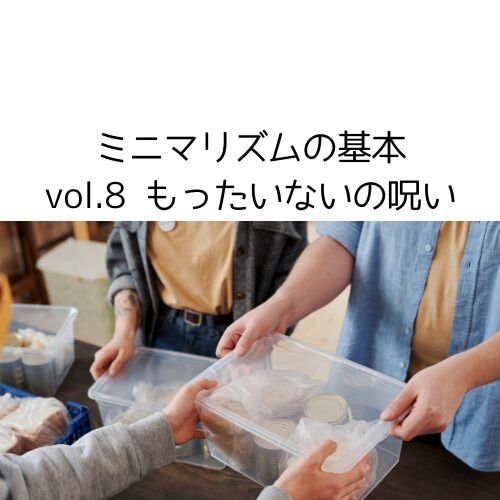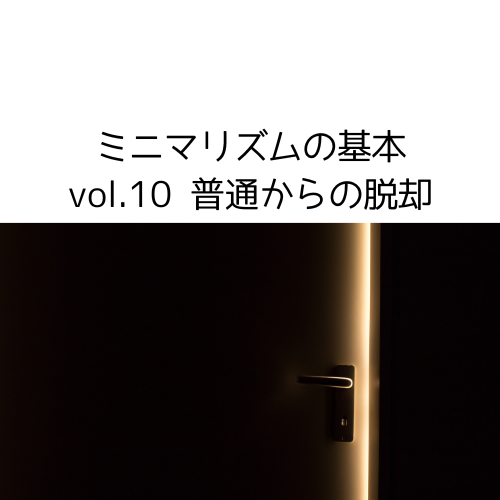こんにちは。ミニマリストで現役医師のえけです。
「ミニマリストのすっきりした部屋、いいな」
「自分もモノを減らして、もっと身軽に暮らしたい」
そう思って片付けを始めてみたものの、
「何から手をつけていいか分からず、結局そのまま…」
「一度に全部やろうとして、途中で疲れて挫折してしまった…」
そんな経験はありませんか?
かつての僕もそうでした。
ご安心ください、ミニマリズムで挫折してしまうのは、
あなたの意志が弱いからではありません。
始め方にちょっとしたコツが必要なだけなのです。
この記事では、医師の視点も交えながら、誰でも無理なく、
そして「挫折せず」にミニマリズムを始めるための具体的な3つのステップをご紹介します。
完璧なミニマリストを目指す必要はありません。
一緒に、あなたらしい心地よい暮らしの第一歩を踏み出しましょう。
なぜ、私たちはミニマリズムで挫折してしまうのか?
まず、挫折の原因を知ることで、対策が立てやすくなります。
原因1:最初から「完璧」を目指しすぎている
SNSで見かけるような、モデルルームのような部屋。
それをいきなり目指してしまうと、現実とのギャップに心が折れてしまいます。
実は、過度な完璧主義が、時に心の不調につながることは医療の現場でもよく見られます。
ミニマリズムは「何もない状態」がゴールではありません。
最初から100点を目指すのではなく、
まずはマイナスをゼロにするくらいの気持ちで始めましょう。
完璧主義は、うつ病、強迫性障害、摂食障害、不安障害などの発症や増悪要因となることが
臨床的にも疫学的にも示されています
原因2:モチベーションだけで乗り切ろうとする
「よし、やるぞ!」と意気込んで休日に一日中片付け。
しかし、終わりが見えない作業に脳も体も疲れ果て、
翌週にはもうやる気がなくなってしまう…。
これは、人間の脳が急激な変化よりも、小さな習慣の継続を好む性質
(ホメオスタシス:体を一手に保とうとする働き)を持っているためです。
モチベーションは必ず波があります。
大切なのは、やる気に頼らない「仕組み」を作ることです。
原因3:「捨てる」ことへの罪悪感
「もったいない」「まだ使えるのに…」という罪悪感も、大きな壁になります。
もちろん、モノが捨てられないこと全てが病気というわけではありません。
しかし、もしそれが日常生活に深刻な支障をきたすほどであれば、
「ためこみ症(Hoarding Disorder)」という専門的なサポートが必要な疾患の場合もあります。
この罪悪感をどう乗り越えるかが、挫折しないための大きなポイントです
挫折しない!ミニマリズムを始めるための3ステップ
お待たせしました。
ここからは、やる気に頼らず、誰でも無理なく始められる具体的な3ステップをご紹介します。
ステップ1:「理想」ではなく「不快」を取り除くことから始める
「理想の暮らし」を思い描くのは、意外と難しいものです。
そこで、まずは逆の発想をしてみましょう。
「今の暮らしの、ちょっとした不快な点はどこだろう?」と考えてみるのです。
- 「いつも探し物をしてしまう、ごちゃごちゃの引き出し」
- 「郵便物やチラシが溜まって、なんとなく落ち着かないテーブルの上」
- 「着たい服がすぐに見つからないクローゼット」
まずは、この「小さな不快」を一つだけ解決することを目標にしてみましょう。
例えば、「今日はこの引き出しの中だけ整理する」と決める。
すると、ゴールが明確になり、達成感も得やすくなります。
この小さな成功体験が、次への大きな一歩になるのです。
実は、「探し物をする」といった小さなイライラでも、
私たちの脳の扁桃体(不安や恐怖を司る部分)は反応し、
ストレスホルモン「コルチゾール」が分泌されます。
これが毎日繰り返されると、気づかぬうちに慢性的なストレス状態に。
まず「不快な場所」を1つ解消することは、
このストレス源を断ち切るという、
メンタルヘルスにおける非常に合理的な応急処置なのです。
ステップ2:「1日1捨て」で捨てるハードルを下げる
一気に片付けようとすると、判断に疲れ、挫折につながります。
そこでおすすめなのが、ゲーム感覚でできる「1日1捨て」です。
ルールは簡単。1日に1つだけ、何かを手放す。これだけです。
ポイントは、判断に迷わないモノから始めること。
- 明らかにゴミだとわかるモノ(壊れたもの、空き箱など)
- インクが出なくなったペン
- 期限切れの試供品やクーポン券
「1日1個だけ?」と思うかもしれませんが、
これを続ければ1年で365個のモノが家からなくなります。
捨てる行為に慣れる「準備運動」として、これ以上ない最適な方法です。
「1つ捨てられた」という小さな目標達成は、
脳内で快楽物質である「ドーパミン」を放出させます。
これが脳の「報酬系」を刺激し、
「気持ちいい」「またやりたい」というポジティブな感情を生み出します。
この快感の積み重ねが「自分にもできる」という自己効力感を育み、
挫折しにくい「捨て体質」への好循環を作り出すのです。
ステップ3:「入れる」を止め、「出口」の習慣を作る
モノを減らす(出口)と同時に、新しいモノを家に入れない(入口)意識を持つことが、
リバウンドしないために非常に重要です。
- 「とりあえず」で買わない;
- 「安いから」「限定だから」で買うのをやめ、
- 「これは本当に今の自分に必要か?」と一度立ち止まって考えてみましょう。
- 無料のモノをもらわない勇気;
- 街で配っている試供品や景品など、無意識に受け取っていませんか?
- 「結構です」と断る勇気も、立派なミニマリズムの実践です。
- 「1つ買ったら、1つ手放す」;
- 新しい服を1枚買ったら、クローゼットから1枚手放す。
- この「1 in 1 out 」のルールを徹底すると、モノの総量を一定に保つことができます。
私たちの脳、特に理性や判断を司る前頭前野が1日に使えるエネルギーには限りがあります。
買い物などで選択と決断を繰り返すと、脳はエネルギーを消耗し「決断疲れ」を起こします。
「1 in 1 out」のようなルールを設けることは、この脳のエネルギー消費を節約し、
本当に大切なことへの判断力を温存するための、非常に有効な戦略と言えるのです。
ミニマリズムは「ゴール」ではなく「ツール」
最後に一番大切なことをお伝えします。
モノを減らすこと自体が、ミニマリズムの目的ではありません。
ミニマリズムとは、
「自分にとって本当に大切なこと」を見極め、
そこに時間やお金、エネルギーといった限りある資源を集中させるためのツール(手段)です。
あなたにとって大切なものが
「家族との時間」なのか、「趣味に没頭すること」なのか、「仕事で成果を出すこと」なのか。
それは人それぞれ違っていいのです。
他の誰かと比べる必要はありません。
あなたらしい心地よい暮らしを作るための道具として、ミニマリズムを役立ててみてください。
☑️ 今日のミニマリズムアクション
いつか使うかもと思っている試供品を1つ捨ててみましょう。
これが、あなたのミニマリズムの記念すべき第一歩です!